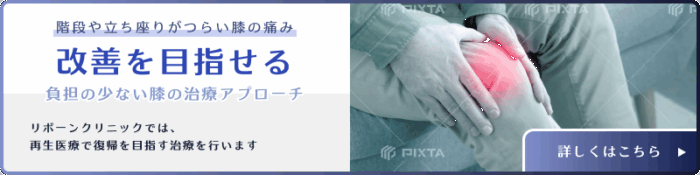変形性膝関節症
リボーンクリニック 大阪院の変形性膝関節症
変形性膝関節症 禁忌とは?してはいけない姿勢と動作を徹底解説

変形性膝関節症 禁忌とは?やってはいけない動作や姿勢を徹底解説
変形性膝関節症は、膝の軟骨がすり減り、痛みや腫れ、可動域の制限などを引き起こす進行性の疾患です。しかし、日常的に避けるべき“禁忌動作”や“禁忌肢位”を正しく理解すれば、膝への負担を大きく減らし、進行を遅らせることが可能です。
この記事では、膝に負担をかける危険な動きや、知らずにやってしまいがちな生活習慣について、専門的な視点からわかりやすく解説します。膝を守る歩き方や、家具選び、靴やサポーターの活用法まで、すぐに取り入れられる実践的なアドバイスをご紹介。
変形性膝関節症の方が避けるべき「やってはいけない動き」や「避けるべき姿勢=禁忌肢位」について、最新の知見をもとにわかりやすく具体的に解説しました。さらに、生活習慣や職場環境、サポーター・靴の選び方、自己流リハビリの注意点まで網羅的に取り上げ、膝への負担を減らすための実践的なヒントをお届けします。
膝を守りたい方、進行を防ぎたい方にとって、きっと役立つ情報が見つかるはずです。
ぜひ最後まで読み進めてください。
-
この記事で分かること
- ☑ 変形性膝関節症における禁忌肢位、やってはいけない動作
- ☑ 正座・しゃがみ込みなど膝を悪化させる動作
- ☑ 和式トイレや床生活など日常に潜むリスク
- ☑ 膝への負担を減らすための姿勢や生活環境の工夫
- ☑ 自己流リハビリや運動の注意点と専門家の重要性
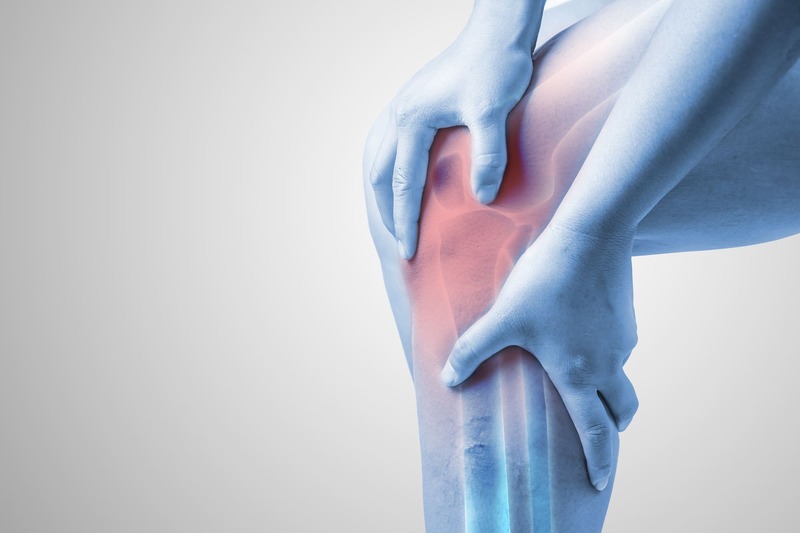
変形性膝関節症 禁忌肢位とは?避けるべき動きと姿勢
変形性膝関節症の方が日常生活で気をつけるべきなのは、「膝に強い負担をかける姿勢や動作」です。これを医学的に「禁忌肢位(きんきしい)」と呼びます。
禁忌肢位とは、膝関節に対して過度な圧力や不自然なねじれが生じる姿勢のことで、症状の悪化や痛みの増強を引き起こすリスクがあります。たとえば、深くしゃがみ込んだり、正座をする、床に直に座るといった動作がこれに当たります。
なぜ、これらが良くないのか?膝を90度以上に曲げることで関節内の圧力が急激に高まるからなのです。その結果として、すでにすり減っている関節軟骨にさらなるダメージが加わり、炎症や痛みを強めてしまうことになります。
特に注意すべきなのは、「しゃがみ動作」や「膝に体重を乗せた状態での膝曲げ姿勢」です。掃除や布団の上げ下ろし、床に対して直に、あぐらやペタンとした座り方をするのは控えていただきたいのです。つまりは、最近は少なくなりましたが和式トイレなどを日常的に使うのはお勧めできないです。
膝関節は、立ち上がり・座る・歩くといった基本的な動作すべてに関与しているため、ちょっとした動作の積み重ねが悪化の原因になりかねないためご注意ください。以下の項目で、それぞれ詳しくご説明してまいります
- POINT
- ●禁忌肢位とは膝に過度な負担がかかる避けた方が良い姿勢のこと
- ●膝を90度以上に深く曲げる動作が特に危険
- ●床での生活習慣(和式トイレ、布団、正座など)は見直しが必要
| 禁忌動作・姿勢 | 膝への影響 | 推奨代替動作 |
|---|---|---|
| 正座 | 関節への強い圧迫 | 椅子に浅く腰掛ける |
| しゃがみ込み | 関節軟骨の摩耗促進 | 片膝つき姿勢など |
| 階段の昇降 | 衝撃とねじれの複合負荷 | エレベーター使用 |
| 和式トイレ | 過屈曲によるストレス | 洋式トイレを使用 |
| 長時間の立位 | 関節疲労・炎症リスク | こまめな休憩 |
変形性膝関節症のやってはいけない、禁忌肢位とは何か
膝に痛みを抱えている方にとって、「禁忌肢位」という言葉は聞き慣れないかもしれません。しかしこれは、症状を悪化させないために非常に大切な考え方です。
変形性ひざ関節症でやってはいけない、禁忌肢位とは、「関節に無理な力がかかる姿勢」を指します。具体的には、膝の関節に強い圧迫が加わる動作や、不自然な角度での保持、急な捻りなどが含まれます。
例えば、前項でも申しましたが、床に座って正座を続けたり、低い姿勢で長時間作業をしたりすることは、関節にとって非常に負担となります。関節内にある軟骨がすり減っている状態で強く圧迫されると、さらに摩耗が進行し、回復の妨げとなる恐れがあるからです。
また、禁忌肢位は個人の関節の状態によっても変わります。膝が強く変形している場合、ほんの少しの曲げ伸ばしでも炎症が起きることがあるため、無理のない範囲での動作に切り替えることが必要です。
「膝を守る姿勢」を日常に取り入れることが、痛みの軽減や症状の進行予防につながります。
- POINT
- ●禁忌肢位とは膝に無理な負担をかける姿勢
- ●関節軟骨への圧力が強くなる体勢は避ける
- ●個々の状態に応じて許容できる動作は異なる
正座・しゃがみ込みはなぜ危険か
普段の生活で自然と行ってしまいがちな「正座」や「しゃがみ込み」。これらの動作は、日本の生活習慣に根づいたものですが、変形性膝関節症の方にとっては、かなり注意が必要です。
というのも、これらの姿勢は膝関節を深く曲げることで、関節内にかかる圧力が非常に高くなるためです。すでに損傷がある軟骨や半月板には、さらに強い負荷がかかり、炎症や痛みの悪化を招いてしまいます。
例えば、正座の姿勢では膝が完全に折りたたまれ、自身の体重がそのまま膝にかかります。この状態が数分でも続けば、関節内の血流が悪化し、違和感やこわばりの原因となります。
また、しゃがみ込んだ姿勢から立ち上がるときには膝に大きな力がかかるため、痛みを誘発しやすくなります。こうした動作を繰り返すことで、軟骨の摩耗や膝関節の変形が進行するリスクが高まります。
― 生活の中でこれらの動作が必要な場面では、以下のような工夫を取り入れてみましょう。
- ●正座は椅子や正座補助具を使って代用する
- ●しゃがみ作業はできる限り中腰か椅子で対応
- ●布団よりベッド、和式トイレより洋式トイレを使う
- ●様式の生活を取り入れましょう
こうした日々の小さな見直しが、将来的な膝の状態を左右します。
和式トイレが膝に与える悪影響
変形性膝関節症の方にとって、和式トイレの使用は膝への負担が大きく、避けたい習慣のひとつです。見た目には些細なことのように思えるかもしれませんが、しゃがみ込む姿勢は膝関節に強い圧力を加えるため、やってはいけない典型的な「禁忌肢位」です。
和式トイレを使用する際の体勢では、膝が深く曲がるだけでなく、太ももの筋肉が膝関節を押しつぶすような力が働きます。このとき、関節内圧は大きく上昇し、すでにすり減っている軟骨や変形した骨にさらなるダメージを与えるリスクがあります。
特に高齢者の場合は、膝を深く曲げたままの状態から立ち上がる動作も難しく、転倒の危険性も高まります。これらの理由から、膝に不安がある方にとって和式トイレは非常に不向きといえるでしょう。
現在では、ほとんどの施設や家庭で洋式トイレの設置が進んでいますが、万一、ご自宅のトイレが和式のままという方は、膝の負担軽減の観点からも、洋式への切り替えを検討されることをお勧めします。
- POINT
- ●和式トイレの姿勢は膝に強い圧力をかける
- ●立ち上がり時の膝への負担も大きい
- ●洋式トイレへの変更が望ましい
和式の床生活が膝関節に与えるリスク
畳の部屋での生活や、床に直接座る生活スタイルは、日本では古くから親しまれてきた文化のひとつで、日本ならではの落ち着いた風情を感じます。ただし、それも変形性膝関節症の方にとっては、その床生活が思わぬ悪化要因となることは、ここまで何度も述べさせていただきました。
床に座る姿勢では膝を深く曲げたり、横に倒したりする動きが自然と増えるからです。あぐら、ぺたんこ座り、体育座りなど、いずれも関節に過剰なねじれや圧迫を加えてしまいます。また、床からの立ち上がりには大きな負荷がかかり、膝の痛みを誘発しやすくなる点も見逃せません。
特に布団で寝起きしている方は、毎日の布団の上げ下げや、しゃがんだ姿勢からの立ち上がりが習慣となっていることが多く、膝に慢性的なストレスを毎日のように与え続けてしまうことになります。
このような床生活を続けていると、日々の動作が小さなダメージとなり、気づかぬうちに症状が悪化するケースもあり、できれば洋室へのリフォームまでとは申しませんが、次のような工夫を取り入れることで負担を大きく減らすことができます。ご検討ください。
- POINT
- ●様式の膝に負担のない生活を目指す
- ●座椅子や椅子を使用し、膝の深い屈曲を避ける
- ●ベッドでの就寝に切り替え、起き上がりを楽にする
- ●布団の上げ下ろしは家族に任せる、またはやめる
生活環境の見直しは、膝の負担軽減に直結します。無理のない範囲から少しずつ変えていくことが大切です。
スクワットやジャンプはしてはいけない?
運動不足の解消や筋力強化に良いとされる「スクワット」や「ジャンプ」ですが、変形性膝関節症の方にとっては注意が必要です。これらの運動は膝にかかる負担が大きく、状態を悪化させる危険性があります。特に若い方にとっては大切なトレーニングであっても膝に痛みを持たれている方には、やってはいけない動作になります。
スクワットは一見すると飛び跳ねる訳ではなく、ゆっくり行えれば安全なトレーニングに思えますが、自分の体重を膝で支えながら深く曲げる動作は、実際には関節に強い圧力がかかります。膝の軟骨がすり減っている状態では、この負荷が炎症や痛みを引き起こす原因になってしまいます。
また、ジャンプ運動は、着地時に体重の数倍もの衝撃が膝に加わるため、軟骨や靭帯を痛めるリスクが非常に高いのです。バスケットボールやバレーボール、バスケットボールなど、反復してジャンプを行う運動は特に避けてください。
このような運動は行わないという、ご年代の方にとってもスクワットなどは、膝の運動として行っていたり、ちょっとした飛び移りなど、軽いなジャンプを知らず知らずに行ってしまうこともありまので、やってはいけない動作という認識をお持ちいただければと思います。
一方で、すべての運動が悪いというわけではありません。むしろ、膝を守るためには筋力を維持・強化することがとても重要です。ただし、その方法は膝への衝撃が少ないものを選ぶ必要があります。自己判断は避けて、医師またはリハビリの理学療法士など専門家のアドバイスに従い安全に行いましょう。
― 以下のような運動なら、安全に筋力を保つことができます。
- ●椅子に座ったまま足を上げるレッグエクステンション
- ●水中ウォーキングで浮力を利用した負荷
- ●軽いストレッチで関節の可動域を維持
無理な負荷を避け、継続できる運動を選ぶことが、痛みを予防し膝の健康を守るコツです。
長時間の歩行や立ち仕事がNGな理由
変形性膝関節症の方にとって、長時間の歩行や立ちっぱなしの作業は、膝関節に過剰な負担をかける大きな要因となります。特に症状が進行している段階では、こうした日常動作が痛みの増強や悪化を招きやすくなるため注意が必要です。
歩く・立つという行為そのものは健康的で、筋力維持にもつながりますが、長時間続けることによって膝の関節軟骨が圧迫され、摩耗が進みやすくなるリスクがあります。特に硬い地面やクッション性のない靴での歩行・立ち仕事は、衝撃がダイレクトに膝へ伝わりやすいため、見過ごせません。
実際、スーパーのレジ業務、工場での立ち作業、長時間の外回りなど、同じ姿勢を続ける職業では、膝への慢性的なストレスによって痛みが慢性化するケースが多く見られます。
とはいえ、まったく歩かない、動かないというのも逆効果です。膝周囲の筋力が衰えてしまえば、関節を支える力が弱まり、症状をさらに悪化させることにつながります。大切なのは、「適度な時間での歩行や休憩を取り入れること」です。
- POINT
- ●長時間の歩行・立ち仕事は膝軟骨を圧迫し悪化要因になる
- ●硬い床面やクッション性のない靴は衝撃が強くなる
- ●短時間ごとに休憩や姿勢の変更を取り入れることが望ましい
階段の昇り降りが膝に負担をかける理由
階段の昇り降りは、日常の中で避けにくい動作の一つです。しかし、変形性膝関節症を抱えている方にとっては、この上下動作が膝に大きなストレスを与える危険な動きとなります。
その理由は、階段を上がる際には膝を強く伸ばす力、下りる際には体重を受け止める衝撃が加わるからです。特に下り階段は、着地のたびに膝へ体重の3〜5倍もの圧力がかかるとされており、これが炎症や痛みの直接的な原因になります。
さらに、筋力が衰えている場合には、体を支えるバランスを崩しやすくなり、転倒のリスクも上昇します。下りるときにガクンと膝が抜けるような感覚を経験した方も少なくないのではないでしょうか。
対策としては、エレベーターやエスカレーターの利用を積極的に取り入れることが第一です。どうしても階段を使わなければならない場合には、手すりを必ず使い、ゆっくり一段ずつ、体重を分散させながら昇降するようにしましょう。
- POINT
- ●階段の昇降時は膝に強い圧力や衝撃が加わる
- ●特に下りは体重の数倍の負荷がかかる
- ●エレベーターや手すりの活用で負担を軽減できる
| 生活場面 | NG動作例 | 推奨環境・工夫 |
|---|---|---|
| トイレ | 和式便器を使用 | 洋式便座に変更、手すり設置 |
| 居間 | 床に座る | 椅子+テーブル生活へ変更 |
| 寝室 | 低すぎる布団 | ベッド+膝に優しいマットレス |
| 台所 | しゃがみ作業 | 高さ調整可能な作業台を使用 |
急な動きや方向転換の危険性
変形性膝関節症の方にとって、急な動きや方向転換は、膝の関節にねじれや衝撃を生みやすく、非常に危険な動作です。無意識に行ってしまいがちですが、関節内部の構造には想像以上のダメージが加わっていることがあります。
急な方向転換とは、例えば、人に呼ばれて急に振り向く、歩行中に急停止して方向を変えるといった動きです。これらの動作では、体の上半身と下半身が異なる方向に動くため、膝関節がひねられやすくなります。関節の変形や軟骨のすり減りがある状態では、このねじれが痛みを引き起こすだけでなく、炎症や関節水腫の原因になることもあります。
また、筋力が低下している方や反応が遅くなっている高齢者の場合は、バランスを崩して転倒してしまうリスクも高まります。とっさの動きが膝に深刻なダメージを与える可能性があるため、できるだけ「ゆっくり・確実に動く」ことを心がけてください。
特に人混みや狭い場所では、前方不注意や他者との接触によって急な動作が発生しやすいため、環境に応じた慎重な行動が求められます。動くときは「ゆっくり確実に」を意識しましょう。
- POINT
- ●急な方向転換は膝関節にねじれと衝撃を与える
- ●関節の変形状態では痛み・炎症を誘発しやすい
- ●「ゆっくり確実に動く」意識が予防につながる
関節が冷える環境も禁忌肢位に影響する
禁忌は、関節の動きだけを気にすれば良いのではありません!関節の「冷え」は変形性膝関節症にとって無視できないリスク要因のひとつだからです。冷えそのものが直接、関節の構造を壊すわけではありませんが、禁忌肢位の悪影響を強めてしまう場合があります。
冷えによって筋肉や靭帯の柔軟性が低下すると、膝を曲げ伸ばしする際に関節周囲の動きが硬くなり、通常以上に負担がかかりやすくなります。その状態で正座やしゃがみ込みなどの禁忌姿勢を取れば、膝の可動域が狭まっている分、関節への圧力はより高まり、炎症や痛みの原因となってしまうのです。
さらに、血流が悪くなることで、関節内の修復や代謝機能が落ち、炎症が慢性化しやすくなる点にも注意が必要です。冬場の外出や冷えた室内、クーラーの効いた環境などでも冷え対策は重要になります。
|冷えから膝を守るために、以下のような工夫が効果的です。
- ●膝にレッグウォーマーや保温サポーターを着用する
- ●床暖房やこたつを利用する際も直接冷気に触れないようにする
- ●入浴や足湯で膝周りを温め、血流を促す
このように、膝関節の冷えを防ぐことは、禁忌肢位の影響を軽減し、痛みの予防にもつながります。
変形性膝関節症 禁忌と生活改善のポイント
変形性膝関節症において、「禁忌」とされる動作を避けることはもちろん大切ですが、それに加えて日常生活の中で膝への負担を減らす工夫をすることが、進行の予防や、痛みの軽減には不可欠です。
膝にやさしい生活とは、言い換えれば「膝関節に余計な圧力やねじれをかけない動作を習慣づけること」です。床に座らず椅子を使う、立ち上がる際には手を使って補助する、歩く距離を調整するといった行動が、長期的に見ると大きな差につながってきます。
また、生活の中で見落とされがちなのが「動線の改善」です。例えば、自宅の中で頻繁に階段を使う必要がある、買い物時に重たい荷物を片手で持つといった些細なことが、膝にとっては大きな負担となります。買い物カートやキャリーケース、杖などを上手に取り入れることで、関節へのストレスを軽減できます。
もちろん、完全に動かさないのもNGです。軽いウォーキングや筋トレなど、膝にやさしい運動を取り入れることも、予防には有効です。
- POINT
- ●椅子中心の生活に切り替える
- ●階段や買い物など日常動作の見直しがカギ
- ●膝へのやさしい運動は継続することが大切
生活習慣のひと工夫が、膝関節の健康寿命を伸ばすポイントとなります。
肥満が膝関節に与える影響と対策
体重の増加は、変形性膝関節症の最大のリスク因子のひとつです。特に肥満の状態では、歩くたびに体重の2倍以上の力が膝関節に加わるとされており、それが慢性的な軟骨のすり減りや炎症を引き起こす原因になります。
例えば、体重が1kg増えるごとに、膝への負荷は3kg以上増すといわれ、わずかな体重増加でも膝に与える影響は決して小さくありません。これは、禁忌肢位とされるような動作を避けていても、膝関節が常に高い圧力にさらされる状態になることを意味します。
ただし、急激なダイエットは筋肉量の低下につながり、かえって関節を支える力を弱めてしまう可能性もあるため要注意です。無理のない範囲で「筋肉を残しながら体脂肪を減らす」ことが、膝にやさしいダイエットの基本となります。医師やリハビリ担当者の助言を受けましょう。
― 以下は、膝関節への負担を減らすための肥満対策の一例です。
- ●糖質や脂質を抑えた食事をバランスよく続ける
- ●プールでの運動や、低負荷のウォーキングを習慣化する
- ●筋力維持のために、簡単な下肢トレーニングを継続する
体重管理は、膝への負担を根本から減らす数少ない「直接的な予防策」です。体の重みを見直すことは、膝を守る第一歩といえるでしょう。
禁忌動作を避ける歩き方の工夫
変形性膝関節症を抱える方にとって、日々の「歩き方」は膝への負担を大きく左右する要素です。特に、禁忌とされる動作である「膝を深く曲げたり、急に方向を変える動き」を自然と避けられる歩き方を身につけることが、痛みの軽減と進行の予防につながります。
例えば、歩幅が大きすぎたり、足を引きずるような歩き方は、関節に余計なストレスをかける原因になります。歩く際は「小さめの歩幅」「膝を伸ばしきらず軽く曲げた状態を保つ」「かかとから着地し、つま先で蹴り出す」ことを意識しましょう。これにより、衝撃を和らげ、膝への負担を減らすことができます。
さらに、路面の状況も意識したいポイントです。段差の多い道、傾斜のある坂道、濡れて滑りやすい場所などは、膝へのねじれや転倒リスクが高まるため、可能であれば避けるか、慎重に歩くことが求められます。

ロフストランドクラッチ、杖
また、痛みの出やすい方は、杖やロフストランドクラッチなどの歩行補助具を使うことで、身体のバランスを保ちつつ膝の負担を分散できます。
- POINT
- ●歩幅を小さく保ち、膝を伸ばしきらない
- ●かかと着地・つま先蹴り出しの基本を意識する
- ●歩行補助具(杖、ロフストランドクラッチ)の使用も検討する
日常生活での膝負担を減らす姿勢と家具選び
家庭内で過ごす時間は、膝を休めるチャンスでもありますが、逆に知らず知らずのうちに膝へ負担をかけてしまっていることもあります。特に座り方や家具の高さといった生活環境の選択は、症状の悪化に直結するため見直しが必要かもしれません。
たとえば、低いソファや座椅子に深く座り込むと、立ち上がる際に膝を大きく曲げる必要があり、これが軟骨や靭帯に強い圧力をかけることになります。そのため、膝を90度程度に保てる「適度な高さの椅子」が理想です。立ち上がるときに手すりやひじ掛けを使えると、より安全に動作できます。
また、ダイニングテーブルや洗面台など、生活動線上の「高さ」も要チェックです。膝を必要以上に曲げたり、中腰姿勢になりやすい環境は、長期的に見ると膝の負担になります。
床生活(座布団・ちゃぶ台)から椅子・テーブル中心の生活へ切り替えるだけでも、膝への負担は大きく軽減されます。寝具もベッドタイプにすることで、起き上がり・立ち上がりの動作をスムーズにできます。
- POINT
- ●椅子は膝が直角に曲がる高さを選ぶ
- ●立ち上がりにはひじ掛けや手すりを活用する
- ●床生活から椅子・テーブル中心の生活へ切り替える
仕事での禁忌動作と職種別の注意点
働いている方にとっては、業務中の姿勢や動作が変形性膝関節症の悪化要因となってしまう場合もあります。特に、一定の姿勢を長時間続けたり、膝に負担のかかる動きを頻繁に繰り返す職種では、意識的に工夫をすることが求められます。
立ち仕事が中心の販売・飲食・介護業では、長時間の直立や前屈み姿勢が続くことで、膝関節への圧力が高まります。このような場合は、足元にクッションマットを敷いたり、休憩時には椅子に座って脚を高く保つなど、こまめな休息と膝の回復がポイントになります。
一方、座りっぱなしの事務職でも油断はできません。長時間同じ姿勢でいることで膝周囲の筋肉が硬直し、立ち上がったときに強い痛みを感じるケースがあるため、1時間に一度は定期的に立ち上がってストレッチをするなど、適度な運動が必要です。
さらに、建設業や農作業などのようにしゃがむ・膝をつく動作が多い職種では、膝パッドやクッションを活用するだけでなく、できるだけ膝を曲げずに作業できる代替方法を検討しましょう。
| 職種 | 動作例 | 膝への負担 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 介護職 | 屈伸・持ち上げ動作 | 高 | 膝を曲げる作業が多いため、補助具利用 |
| 保育士 | 床作業・抱っこ | 中 | 長時間の膝屈曲姿勢に注意 |
| 調理師 | 長時間立位 | 中 | クッションマット使用など推奨 |
| デスクワーク | 座りっぱなし | 低〜中 | 足を組まず正しい姿勢を保つ |
- POINT
- ●立ち仕事にはクッション性の高い靴や足元マットを活用
- ●デスクワークでも定期的に足を動かす工夫をする
- ●膝をつく作業ではサポーターやクッションで保護する
サポーターや靴選びで膝の負担を軽減する方法
膝に不安がある方にとって、サポーターや靴の選び方は、見落とされがちですが非常に大切なポイントです。正しく選ぶことで、膝への負担を軽減し、日常動作を快適にすることができるからです。
サポーターには、膝のぐらつきを抑え、関節の安定性を高める役目があり、様々なタイプがあります。特に変形性膝関節症の初期や中期の方は、「軽度圧迫型」や「ヒンジ付きサポーター」が適しています。これにより、関節の横揺れや過伸展を防ぎ、無意識のうちに膝にかかるストレスを軽くすることが可能です。
一方で、サポーターを長時間つけすぎると、筋肉が弱まって逆効果になる場合もあるため、必要な場面だけに限定して使用することが望ましいため。こちらも医師やリハビリの専門家に膝の状況に合わせたアドバイスをもらいましょう。
靴選びについては、「クッション性」「安定性」「足へのフィット感」が重要です。かかとが安定し、つま先が少し上がった形状の靴は、着地時の衝撃を緩和し、膝への振動を抑えることができます。また、ソールが硬すぎると膝に直接衝撃が伝わりやすいため、適度に柔らかい素材を選びも大切です。
さらに、インソール(中敷き)を活用することで、足裏のアーチをサポートし、膝の軸が安定しやすくなります。既製品でも良いですが、症状が重い方は整形外科などで自分専用のオーダーメイドインソールを作るのもひとつの方法です。オーダーは整形外科等の医療機関で行うのが確実です。
| 製品タイプ | おすすめ度 | ポイント |
|---|---|---|
| クッション性の高い靴 | ◎ | 衝撃を吸収し膝への負担軽減 |
| ヒールの高い靴 | × | 膝への圧力が増す |
| 硬すぎる靴底 | △ | 衝撃が直接伝わりやすい |
| 膝を包むサポーター | ◎ | 安定性が増し動作時の負荷を軽減 |
- POINT
- ●サポーターは膝の安定性を補助するが、使いすぎに注意
- ●靴はクッション性・フィット感・安定性を重視する
- ●必要に応じて中敷きやインソールでバランスを整える
無理なストレッチや自己流リハビリはNG
「少しでも良くなりたい」「動かさないと悪化する気がする」との思いから、自己判断でリハビリやストレッチを始める方がいます。しかし、変形性膝関節症の場合、自己流の運動はかえって状態を悪化させるリスクがあります。
痛みを無視して膝を無理に曲げ伸ばしすることや、勢いをつけたストレッチは、関節軟骨への圧力を増やし、炎症を引き起こす可能性があります。また、禁忌とされる動作(深いしゃがみ込みなど)を伴うストレッチは、知らないうちに症状を悪化させる原因にもなります。
特に動画サイトなどで紹介されている一般的なストレッチは、健康な人向けに作られているものが多く、膝にトラブルを抱える方にとっては不適切なものも含まれています。
適切なリハビリとは、「今の膝の状態」に合わせた運動を、医師や理学療法士の指導のもとで行うことです。具体的には、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えるような「膝を動かさない筋トレ(例:セッティング)」や、水中での歩行運動などが、安全かつ効果的です。
なお、症状の程度によっては、ストレッチを全く行わない方が良い場合もあります。自己判断に頼らず、専門家の指示を仰ぐげば安心ですね。
- POINT
- ●痛みを伴うストレッチは逆効果になることがある
- ●インターネットの情報だけで運動を判断しない
- ●リハビリは専門家の指導のもと、安全に進める
まとめ・変形性膝関節症の禁忌を正しく理解して進行を防ごう
変形性膝関節症を悪化させないためには、医療機関での治療だけでなく、日常生活の中で避けるべき禁忌肢位や動作を正しく理解することが非常に大切です。
正座や深くしゃがみ込む動作、和式トイレの使用、階段の昇り降りなどは、膝に大きな負担をかける可能性があります。また、無理なストレッチや自己流のリハビリも、かえって関節を傷めてしまうリスクがあるため注意が必要です。
一方で、適切な歩き方の工夫や、サポーター・靴・家具の選び方、膝を冷やさない環境づくりなど、膝を守るための生活改善はすぐにでも取り入れることができます。特に、膝関節への負担を軽減する姿勢の習慣化や、肥満や筋力低下への対策は、長期的な症状の進行抑制にもつながります。
変形性膝関節症は、正しい知識と行動で“進行を遅らせることができる病気”です。
今回ご紹介した内容を参考に、まずは日々の生活の中でできることから始めてみてください。
あなたの膝を守る第一歩となることを願っています。
よくある質問 Q&A|変形性膝関節症 禁忌(やってはいけないこと)
Q1. 正座は変形性膝関節症に本当に悪いのですか?A. はい、正座は膝を深く曲げた状態が長時間続くため、膝関節への圧力が高まり、軟骨や関節包に負担がかかります。症状の進行や炎症を悪化させる可能性があるため、避けることが推奨されています。 Q2. 禁忌肢位とは具体的にどのような姿勢ですか?A. 禁忌肢位とは、膝に過剰な負担をかけてしまう姿勢のことです。代表的なものには「深くしゃがむ」「膝をねじる」「膝を深く曲げる姿勢(正座など)」があります。これらを避けることで、痛みや進行リスクを軽減できます。 Q3. どのような運動なら膝を悪化させずにできますか?A. 水中ウォーキングや膝に優しいストレッチなど、膝関節に大きな負荷がかからない運動がおすすめです。ただし、自己流で行うのは避け、理学療法士や専門医の指導のもと行うのが安全です。 Q4. 和式トイレの使用はNGですか?A. 和式トイレのように深くしゃがむ姿勢は、膝に大きな負担をかけるため、できる限り洋式トイレを使うことが望ましいです。外出時も多目的トイレや洋式設備を選ぶようにしましょう。 Q5. 禁忌動作を避けるためにできる生活の工夫はありますか?A. はい、床に座る生活を椅子に変える、階段を避けてエレベーターを使う、正しい靴やサポーターを選ぶなど、環境を整えることで膝への負担を大きく減らすことが可能です。生活スタイルを見直すことも治療の一部です。 |
| リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。
国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。 膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。 まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。 |