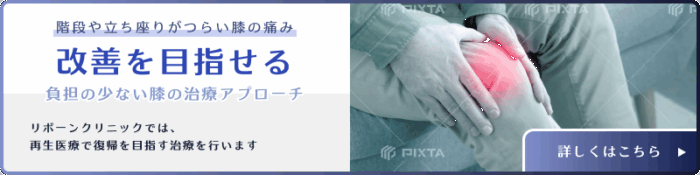変形性膝関節症
リボーンクリニック 大阪院の変形性膝関節症
変形性膝関節症を自力で治す方法|無理せず続ける生活術

変形性膝関節症を自力で治す方法|無理せず続ける生活術
みなさまこんにちは!リボーンクリニックです。
膝の痛みが続くと、毎日の生活にも大きな影響が出てきます。階段の昇り降りがつらい、立ち上がるたびに膝が痛む――実は、こうした症状、「変形性膝関節症の可能性があります」そう聞くと不安になる方も多くおられるのではないでしょうか。
中高年の女性に多く見られるこの疾患は、膝の軟骨がすり減って痛みが発生し、やがて関節が変形へと進行する能性があり、歩行にも支障をきたす場合があります。医療機関での治療を受けることが大切ですが、「まずは自分で何とかしたい」とお考えの方も少なくありません。
そこで本記事では、変形性膝関節症を自力で治したいとお考えの方が実践できる具体的な方法や注意点を、医療的な知識に基づいてわかりやすく解説します。運動療法やストレッチ、体重管理、靴やインソールの選び方、再生医療との違いまで、幅広く網羅しています。
「できることから始めて、少しでも痛みを和らげたい」「進行を抑えて日常を取り戻したい」――そんなあなたのために、セルフケアの可能性と、限界もあることを正しく知ることから始めましょう。
-
この記事で分かること
- ☑ 自力でできる改善・予防方法の具体例(運動・ストレッチ・体重管理など)
- ☑ 保存療法と再生医療の違いや適応の目安
- ☑ サポーター・杖・靴・インソールの正しい選び方と使い方
- ☑ 症状が進行した場合に受診すべきタイミングや対処法
- ☑ セルフケアで得られる効果と限界、その注意点

変形膝関節症 自力で治す
変形性膝関節症を自力で治す…
しょっぱなから辛い結論を申し上げるのは忍びないのですが、実のところ「自力で完治」は現実的ではないのです。変形性膝関節症は進行する疾患で、擦り減った軟骨をご自身のケアだけで止めたり、再生できるものではないからです。ただし、自分で行うケアによっては症状を軽減し、病状の進行を遅らせることは十分に可能です。
今回は、その点から詳しくご説明してまいります。心がけや取り組み次第で、進行を遅らせて快適な生活を続けられる可能性があります。
診察を受けた整形外科等、医療機関では、多くの場合、保存療法(手術をしない治療・リハビリ)が推奨されますが、その中には運動療法や食事管理といった「自分で継続する取り組み」があり、症状の進行を遅らせるために大切になってきます。つまり、保存療法と並行して、自分で行うケアは治療の一部として非常に大切だ!ということです。
実際、初期〜中期の変形性膝関節症では、多くの医師が「太ももの筋力トレーニング」「体重コントロール」「膝に優しい生活動作」との指導を行います。これらはぜひ、自宅で継続して取り組んでいただきたい内容です。
ただし、後期になり、関節の変形が進んでいる場合や、歩行が困難なケースでは、セルフケアには限界があります。悪化を防ぐためには、無理をせず、医師の診断と治療計画を受けましょう。
- ✅ポイント
- ・医師も自力ケアを治療の一環として推奨
- ・特に初期〜中期では自宅ケアが有効
- ・進行度が高い場合は医師との連携が不可欠
変形性膝関節症を自力で治すのは困難
変形性膝関節症は、膝の軟骨が擦り減って起こります、この膝の軟骨なのですが、自然には再生しません。(再生医療という選択肢はありますが…)
なぜなら、軟骨には血管が存在しないため、血流によって栄養や酸素が届けられず、損傷しても修復が困難だからです。そのため、一度すり減ってしまった軟骨が、何もしないで自然に元通りになることや、たとえリハビリを継続したとしても基本的にありません。
また、ヒアルロン酸注射によって、関節の滑りを改善し、痛みを軽減することもできますが、それでも「軟骨自体が元通りに戻る」わけではないのです。
この現実を知ることで、早期からの予防・対処の重要性がより明確になります。放置すればするほど関節の変形は進行するため、できるだけ早く行動を起こすことが、将来の負担を軽くするカギになります。しかも、運動による筋力強化や関節の可動域の維持によって、関節への負担を軽くすることは可能なのです。
最近、この軟骨を修復できる可能性を持った再生医療の幹細胞治療という治療法がスリ減ってしまった軟骨を再生し、痛みをなくしたり、軽減することができるようになりました。新たな選択肢として注目されています。興味がある方は、再生医療専門院である当院までお問い合わせください。丁寧にご説明いたします。
- ✅ポイント
- ・軟骨には自然治癒力がない
- ・放置しても元には戻らない
- ・対処は「予防・進行の抑制」が中心
- ・ただし、再生医療という新たな可能性が生まれた
自力ケアの目的は「進行の抑制」
変形性膝関節症に対する自力ケアの目的は、「症状の進行を抑えること」にあります。
この疾患は、年齢や体重、過去のケガなどを背景にして徐々に進行していくもので、一度進んだ変形や軟骨のすり減りを元に戻すことは困難ですが早い段階で適切な対処をすることで、進行を緩やかにし、痛みや日常生活への支障を最小限に抑えることは可能です。
例えば、体重を5kg減らすだけで、膝への負担が劇的に減少します。また、ウォーキングやストレッチなどの適度な運動は、筋力の維持だけでなく、関節内の血流を促進し、関節機能を守るうえでも役立ちます。
一方で、運動のしすぎや、誤ったフォーム(動き)は、膝を悪化させる原因にもなるため注意が必要です。無理をせず、自分に合った方法を医師と相談しながら実施していきましょう。
- ✅ポイント
- ・自力ケアは「症状の進行を遅らせる」ことが目的
- ・体重管理と運動習慣がカギ
- ・やりすぎや自己流は逆効果のリスクもあり
変形性膝関節症の進行を自力で遅らせる方法とは
変形性膝関節症を完全に治すことは難しいものの、セルフケアであっても正しい方法を継続すれば「進行を抑え」、「痛みを軽減」することは十分に可能です。
自分でできるケアの主な手段には、運動療法、ストレッチ、体重管理、サポーターやインソールの活用などがあります。中でも大切なのは、筋力を維持し、関節にかかる負担を減らすことです。関節周囲の筋肉がしっかり働くことで、膝に直接かかる衝撃をやわらげることができるからです。
例えば、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)を鍛えることで、歩行や階段昇降時の安定性が向上します。また、体重を3kg減らせば、膝への負荷を9〜12kgも軽減できるといわれています。
自力ケアは「地道な継続」がカギです。短期間での完治を目指すのではなく、長く付き合っていく姿勢で取り組むことが、将来の手術リスクを減らす第一歩になります。
| できること | 目的・効果 |
|---|---|
| 太もも(大腿四頭筋)の筋トレを行う | 膝を安定させ、関節への負担を軽減 |
| ストレッチで関節の柔軟性を高める | 動かしやすさを保ち、可動域を維持 |
| 毎日5~15分のウォーキングを続ける | 血行促進と筋力の維持につながる |
| 自転車運動で関節に負担をかけず運動する | 低負荷で膝周りの筋肉を鍛えられる |
| 体重を減らして膝への負担を減らす | 体重1kg減で膝への負担は約3倍軽減 |
| サポーターや杖を正しく使う | 膝の安定性を保ち、痛みを和らげる |
| 靴やインソールを見直す | 歩行時の衝撃を吸収し、膝への負担を軽減 |
| 冷湿布・温湿布を使い分ける | 症状に応じたケアで炎症や痛みを緩和 |
| 膝に負担が少ない生活動作を心がける | 毎日の動作による悪化リスクを防ぐ |
| セルフケアに限界を感じたら病院を受診する | 早期発見・早期治療で進行を抑える |
- セルフケア主な対処法
- ・筋力トレーニング(特に大腿四頭筋)
- ・軽い有酸素運動(ウォーキングなど)
- ・膝にやさしい生活習慣の見直し
- ・正しい靴やサポーターの使用
運動療法で筋肉を鍛えるメリット
筋力をつけることで膝の痛みを軽減できる。これは変形性膝関節症のセルフケアの中でも、非常に効果の高い方法のひとつです。
筋力が弱り、関節が不安定になると、膝の軟骨や骨にかかる負担が増し、変形の進行が早まります。筋力が低下しているとその影響を受けやすくなるため、膝周囲の筋肉を鍛え、支える力を強化することが大切になります。
たとえば、「椅子に座った状態で片脚をゆっくり持ち上げて5秒間キープ」するだけでも、大腿四頭筋を効率よく鍛えることができます。このようなシンプルな運動を取り入れるだけでも、継続すれば大きな効果が期待できます。
一方で、無理に強度の高い運動を行ってしまうと、かえって膝を痛めるリスクもあるため、痛みが出ない範囲で行うことも大切です。
- ✅筋力強化による主なメリット
- ・関節の安定性が向上する
- ・膝にかかる衝撃を分散できる
- ・日常生活の動作が楽になる
- ・将来的な手術リスクを低下できる
ストレッチで柔軟性を高める効果
筋肉や腱の柔軟性を保つことは、膝への負担を軽くするために欠かせません。ストレッチには、血行を促進し、関節の動きをスムーズにする役割があります。
硬くなった筋肉は、動作時の負担を膝関節に集中させてしまう傾向があります。柔軟性を高めることで、膝まわりの筋肉や靱帯がしなやかに動き、膝にかかる力をうまく逃がせるようになります。
たとえば、「床に座って膝を伸ばした状態でタオルを足先にかけ、ゆっくりと足首を手前に引くストレッチ」は、太もも裏やふくらはぎの柔軟性を高めるのに効果的です。
ただし、急に強く伸ばしすぎたり、痛みを我慢しながら行うのは逆効果です。筋肉をじんわり伸ばすような感覚で、リラックスして行うことが大切です。
- ✅ストレッチによる効果
- ・筋肉の緊張を緩和し膝の動きを助ける
- ・血流改善により痛みの軽減が期待できる
- ・運動前後のケガ予防になる
- ・続けることで関節の可動域が広がる
ウォーキングや自転車運動の注意点
適度な有酸素運動は、変形性膝関節症の進行を抑えるうえで有効です。ただし、やり方を間違えると症状を悪化させることにもなりかねませんのでご注意ください。
膝に負担をかけずに筋力を保つためには、「平坦な道でのウォーキング」や、「自転車での軽い有酸素運動」がおすすめです。特に自転車運動は、膝に直接的な衝撃を与えにくく、関節の可動域を広げるトレーニングとしても優れています。
一方で、長時間の運動や、階段や坂道を含むハードなコースは、膝に余分な負担をかけてしまう場合があります。また、運動中に痛みが出たときは中断し、無理をしないことが鉄則です。
特に普段運動をしていなかった方が急に始めると、膝まわりの筋肉が対応できず痛みを悪化させる恐れもあります。最初は1回15分程度から始め、徐々に時間や頻度を増やしていくのが理想です。
- ✅ポイント
- ・平地でのウォーキングから始める
- ・自転車は膝に優しいが、サドルの高さ調整が重要
- ・痛みが出た場合はすぐに中止する
- ・無理せず継続できる強度で行う
体重管理が膝の負担を左右する理由
膝関節は、体重を支える重要な役割を担っており、わずかな体重増加でも膝への負担は非常に大きくなるので注意が必要です。
体重が1kg増えると、平地を歩く際には3~4倍、階段の昇降では6~7倍の重さが膝にかかるといわれています。つまり、体重が5kg増えれば、膝には約15~35kg分の負荷が余分にかかることになります。このような負荷が日常的に続けば、軟骨のすり減りが加速し、変形性膝関節症の進行も早まってしまうという訳になります。
一方で、体重を適正範囲に近づけることで、膝への物理的なストレスは確実に軽減されます。特に肥満傾向がある人は、運動療法の効果を高めるためにも、まずは体重のコントロールを意識しましょう。
急激な減量はリスクも伴うため、炭水化物を控えめにし、たんぱく質と野菜をしっかり摂るなど、栄養バランスの取れた食事を継続することが大切です。
- ✅体重管理で膝に与える影響
- ・歩行時の膝への負担を軽減できる
- ・軟骨の摩耗を抑える効果がある
- ・ダイエットにより炎症や腫れが改善するケースもある
サポーターや杖の正しい使い方
膝に不安定さや痛みがある場合、サポーターや杖を正しく使うことで日常の負担を和らげることができます。
サポーターは、膝関節をしっかり固定しながら、適度に圧迫することで動きをサポートします。膝のお皿周辺を包み込むタイプや、サイドを補強するものなど種類が多いため、自分の症状に合ったものを選ぶことが重要です。過度に締めつけるタイプは血流を妨げる恐れがあるため、適度なフィット感がある製品を選びましょう。医師にアドバイスを受けるのが早道です。
一方、杖の使用には少しコツが必要です。痛みがある側と反対の手で持つことで、体重を分散させることができます。高さの目安は「立ったときに手首の位置にグリップがくる」程度が適切です。低すぎても高すぎても、姿勢を崩し、かえって体に負担がかかります。
サポーターや杖は「年配者が使うもの」といった先入観で避けられがちですが、適切に使えば、膝へのダメージを最小限に抑える効果的なツールになります。
| 補助具 | 主な役割 | 使用タイミング・おすすめの症状 |
|---|---|---|
| サポーター | 膝関節の安定化、筋肉のサポート | 膝のぐらつきや不安定感があるとき運動時や歩行時に痛みが出るとき |
| 杖 | 体重の一部を腕に逃がして負担を軽減 | 体重をかけると強い痛みが出るとき長時間の歩行がつらいとき |
| インソール | 足裏の荷重バランスを調整し膝の負担を軽減 | O脚・X脚による片側の膝に痛みがあるとき歩行時の衝撃を和らげたいとき |
― 使用時の注意点:
- ・サポーターは装着しすぎに注意:筋力低下を防ぐため、長時間の常用は避け、必要な場面で使うのがベストです
- ・杖は反対側で持つのが基本:痛い側の足と反対の手で持つことで、歩行時のバランスが取りやすくなります
- ・インソールは既製品より自分に合ったものを:足型に合っていないと逆効果になることもあるため、医療用や専門店でのフィッティングがおすすめです。
膝に優しい日常生活の習慣とは
日常生活の中にも、膝に負担をかける動作は意外と多くあります。これらを少しずつ見直すだけでも、膝の状態は大きく変わってきます。
和式トイレや正座のように深く膝を曲げる動作は、関節にかかる負担が非常に大きいため、可能であれば洋式トイレの使用や椅子の洋風生活に切り替えましょう。また、階段の昇り降りも膝にかなりの負荷を与える動作ですのでご注意ください。外出先の各種施設では、エレベーターやエスカレーターを積極的に活用しましょう。
さらに、長時間の立ち仕事や重い荷物の持ち運びも、ひざ関節にストレスを与えます。台所仕事の際は足台を用意したり、買い物にはキャリーカートを利用するなど、膝にやさしい選択を日々の中で増やしていくイメージを持つことが大切です。
このように「膝にとってラクな姿勢・動き」を意識することが、症状の進行予防や痛みの軽減に大きくつながります。
- ✅膝を守る生活習慣の例
- ・洋式トイレや椅子生活などの洋風生活を導入
- ・外出先では、階段よりもエレベーターを活用
- ・正座よりもあぐら・脚を伸ばす姿勢
- ・台所や洗面所では高さ調整アイテムを使う
自力ケアで、できること一覧(まとめ)
| ✅ やること | 目的・効果 |
|---|---|
| 太もも(大腿四頭筋)の筋トレを行う | 膝を安定させ、関節への負担を軽減 |
| ストレッチで関節の柔軟性を高める | 動かしやすさを保ち、可動域を維持 |
| 毎日5~15分のウォーキングを続ける | 血行促進と筋力の維持につながる |
| 自転車運動で関節に負担をかけず運動する | 低負荷で膝周りの筋肉を鍛えられる |
| 体重を減らして膝への負担を減らす | 体重1kg減で膝への負担は約3倍軽減 |
| サポーターや杖を正しく使う | 膝の安定性を保ち、痛みを和らげる |
| 靴やインソールを見直す | 歩行時の衝撃を吸収し、膝への負担を軽減 |
| 冷湿布・温湿布を使い分ける | 症状に応じたケアで炎症や痛みを緩和 |
| 膝に負担が少ない洋式の生活を心がける | 毎日の動作による悪化リスクを防ぐ |
| セルフケアに限界を感じたら病院を受診する | 早期発見・早期治療で進行を抑える |
関節水腫(膝に水がたまる)と冷湿布・温湿布の使い分け
関節に「水がたまる」という症状は、膝に炎症が生じたサインのひとつです。このような関節水腫のケアには、冷湿布や温湿布を使い分けることが大切です。
急に膝が腫れて熱をもっている場合には、冷湿布を使用します。冷やすことで血管を収縮させ、炎症を抑える効果が期待できます。運動後や急性の関節痛があるときに適しています。
一方で、痛みが慢性化しており、冷えると違和感やこわばりを感じるような場合には温湿布が適しています。温めることで筋肉の緊張をほぐし、血行を促進させて可動域を広げる効果があるためです。
ただし、炎症が続いている状態で温めてしまうと、かえって症状が悪化することがあります。冷やすべきタイミングで温湿布を使わないよう、膝の状態をよく観察しながら判断しましょう。
| 使用シーン・症状 | 冷湿布(冷やす)がおすすめ | 温湿布(温める)がおすすめ |
|---|---|---|
| 炎症がある場合 | ◎(患部を冷やして炎症を抑える) | ✕(炎症を悪化させる可能性がある) |
| 痛みが突然出たとき(急性期) | ◎(血管を収縮させて痛みや腫れを軽減) | ✕(痛みを悪化させるリスク) |
| 長時間歩いた後の熱感 | ◎(負担がかかって熱を持ったときに冷却) | ✕(逆効果になりやすい) |
| 慢性的なこわばり・重だるさ | ✕(冷やすと筋肉が硬直しやすい) | ◎(血行を促進して筋肉をほぐす) |
| 朝のこわばりがつらいとき | ✕(効果が少ない) | ◎(温めて関節を動かしやすくする) |
| 入浴前後 | ✕(冷やす必要なし) | ◎(入浴後に温湿布で温熱効果を維持できる) |
- ― 使い分けのポイント
- ・急な腫れや熱感 → 冷湿布(冷やす)
- ・慢性痛やこわばり → 温湿布(温める)
- ・状態を見ながら選ぶことが大切
- ・医師や理学療法士に相談するのもおすすめ
靴・インソール選びの重要性
膝にかかる負担は、靴の選び方ひとつでも大きく変わります。特に変形性膝関節症の方にとって、適切な靴とインソールを選ぶことは、日常生活の快適さに直結する重要なポイントです。
膝に優しい靴とは、足裏全体にしっかりフィットし、かかとが安定しているものを指します。ヒールが高い靴や、クッション性の乏しい硬い靴は、地面からの衝撃が膝に直接伝わり、症状の悪化を招くことがあります。
また、オーダーメイドや医療用のインソールを使用することで、歩行時の体重のかかり方を調整し、膝の内側または外側への偏った負荷を軽減することができます。既製品でも、自分の足型に合ったサポート性のあるインソールを選ぶだけで、歩行の安定性が増し、疲れにくくなります。
靴選びにおいては、試し履きの際に「歩きやすさ」と「膝の安定感」を意識して選ぶことが大切です。見た目よりも、機能性と自分の足に合っているかを最優先に考えましょう。
| 特徴項目 | ✅ 適切な靴 | ❌ 不適切な靴 |
|---|---|---|
| 靴底の構造 | クッション性があり、滑りにくい | 硬くて薄い・滑りやすい素材 |
| 靴の形状 | かかとをしっかり包み込む安定した形 | かかとが浅い・サンダル・ミュールなど |
| ヒールの高さ | 2〜3cm程度のローヒール | ハイヒール(4cm以上)、フラットすぎる靴 |
| 素材の柔軟性 | 適度に柔らかく、足になじむ | 固すぎて足にフィットしない |
| フィット感 | 足にしっかり合って、圧迫感がない | サイズが合っていない(大きすぎ/小さすぎ) |
| インソールの構造 | 土踏まずを支えるアーチサポートがある | 平坦なインソールで足裏を支えない |
| 着脱のしやすさ | マジックテープやファスナー付きで調整可能 | 紐がほどけやすい、脱ぎ履きしにくい |
- ― 膝にやさしい靴、インソールの選び方
- ・ヒールが低く、クッション性がある
- ・足全体がしっかりフィットする・医療用インソールやサポートタイプを活用
- ・店頭で必ず歩いて感覚を確認する
再生医療で治る?保存療法との違い
変形性膝関節症の治療には「保存療法」や「手術療法」という代表的な治療法の他に「再生医療」という新たな選択肢が生まれています。それぞれの特徴を理解することで、今後の治療方針を考えるヒントになります。
保存療法は、手術を行わずに痛みや炎症をコントロールする治療法で、薬物療法・ヒアルロン酸注射・運動療法・装具の使用などが含まれます。比較的費用も低く、初期〜中期の症状に有効とされています。ただ、症状が進行した場合には、保存療法では限界があるため、手術といった選択を迫られる場合もあります。
一方で、再生医療は、患者自身の幹細胞を用いて、軟骨の修復・再生を目指したり、炎症を制御し、関節の環境を改善する新しい治療法です。これは、患者さま自身の幹細胞を培養して投与するもので、他にもPRP(多血小板血漿)などを注入する方法もあります。
特に保存療法では改善が難しいケースや、手術を避けたい方にとっては、有力な選択肢となる場合があります。ただし、病状の進行具合や体質によっては効果が限定的なこともあります。また、保険適用外であることなど検討が必要です。当院は、再生医療専門のクリニックです。無理にお勧めすることはございませんので、ご遠慮なくお問合せください。
| 項目 | 保存療法 | 手術療法 | 再生医療 |
|---|---|---|---|
| 対象症状 | 初期〜中期 | ~後期 | 初期~中期〜進行期・手術回避希望者 |
| 主な治療内容 | 運動・注射・薬など | 人工関節置換術・高位脛骨骨切り術 | 幹細胞治療・PRP治療 |
| 効果の範囲 | 痛みや炎症の緩和 | 痛みや炎症の治療 | 軟骨再生・関節環境の修復を期待 |
| 保険適用 | 適用 | 適用 | 自費診療 |
セルフケアで症状が改善しない場合の対処法
変形性膝関節症は進行性の疾患です。自力での対応に限界がある場合や、明らかに日常生活に支障をきたしている場合には、放置せずに医療機関での評価を受けることが大切です。早期の段階で適切な検査や治療を受けることで、今後の進行を食い止められる可能性が高まります。
例えば、歩行時の痛みが強くなった、膝が腫れて曲げづらくなった、階段の昇降が怖くなった…など、これらは進行のサインであることが多いため、自己判断に頼らず医師の診断を仰ぎましょう。
また、最近では整形外科だけでなく、再生医療を扱うクリニックでも詳細な相談が可能です。必要であればセカンドオピニオンも活用し、自分に合った治療方針を見つけてください。
- ※医療機関を受診すべきサイン
- □安静時にも膝がズキズキ痛む
- □膝が腫れて熱をもっている
- □痛みで夜眠れない
- □セルフケアを3カ月以上続けても改善がみられない
まとめ・変形性膝関節症を自力で治す方法を知りたいあなたへ
変形性膝関節症は進行性の疾患ですが、初期~中期であれば、自力で進行を抑えたり、痛みを軽減することは十分に可能です。運動療法やストレッチによる筋力・柔軟性の向上、体重管理、靴やインソールの見直しといった生活習慣の改善が、膝関節への負担を減らし、症状の悪化を防ぐ大切な対策となります。
また、サポーターや杖の正しい使用、日常動作の工夫も、膝に優しい環境づくりには欠かせません。さらに、関節水腫のような症状がある場合には、冷湿布・温湿布を適切に使い分けることでケアがしやすくなります。
一方で、すべてを自分だけで解決しようとするのではなく、症状が改善しない場合には整形外科や再生医療専門クリニックの受診も検討しましょう。医師の診断や指導を受けることで、より安全かつ効果的に対処できる道が広がります。
「変形性膝関節症を自力で治す」ことは、完全な完治を意味するわけではありませんが、日常生活を快適に保つうえで非常に有効です。大切なのは、あきらめず、正しい知識と習慣を積み重ねること。今日からできることを、ひとつずつ始めてみませんか?
よくある質問 Q&A|変形性膝関節症-自力で治す
Q1. 本当に自力で変形性膝関節症は治せますか?A1. 変形性膝関節症は軟骨が擦り減って膝に痛みや炎症が起こります。残念ながら自分で「治す」ことは難しい病気です。ただ、症状の進行を抑えたり、痛みを軽減することは可能です。正しい運動療法や体重管理などを継続することで、膝の負担を減らし、日常生活をより快適に保つことができます。 Q2. 自宅でできる運動はどんなものがありますか?A2. 太ももの筋肉(大腿四頭筋)を鍛える軽いスクワットや、膝を伸ばすストレッチ、椅子に座って行う膝伸ばし運動などがあります。無理のない範囲で、痛みを感じない動作から始めることが大切です。 Q3. 再生医療はどんな人に向いていますか?A3. 保存療法で効果が出にくい方、進行期でも手術を避けたい方、薬や注射以外の選択肢を探している方に向いています。幹細胞治療やPRP療法などがあり、膝関節の軟骨の修復や炎症の抑制を目的としています。 Q4. サポーターやインソールは必ず使うべきですか?A4. 膝のぐらつきや痛みを感じる方には効果的ですが、症状の程度により必要性は異なります。特に歩行時の不安定感がある場合は、専門家のアドバイスを受けながら適切なタイプを選ぶと安心です。 Q5. いつ病院を受診すべきか目安はありますか?A5. 自力でのケアには限界があります。症状が改善しない場合、日常生活に支障が出てきた場合、または膝が腫れて熱を持つような状態が続く場合には、早めに整形外科の受診を検討してください。誤ったケアでは症状が悪化することもあります。医師のアドバイスや、理学療法士など、リハビリ担当者の指示に従ったケアが理想です。 |
リボーンクリニックは、再生医療専門のクリニックです。
国が定めた「再生医療等安全性確保法」のもと、特定認定再生医療等委員会の厳格な審査を経て、厚生労働大臣へ届出を終えた、ご信頼いただける安心の「再生医療専門の医療機関」です。
膝の治療にあたりましては、法令を遵守し、院長の青木医師をはじめとした経験豊富な医師が患者さまのお悩みに親身に寄り添い、最新鋭の設備と熟練のスタッフといった最高の環境でサポートいたします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください(無理に治療をお勧めすることは一切ございません)。